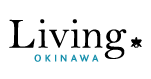那覇の国際通りの喧騒を後にして少し歩くと、足元のアスファルトが琉球石灰岩の石畳に変わり、沖縄のやちむん(焼き物)の街のメインストリートである壺屋やちむん通りに入ったことを告げる。通りには装飾タイル張りの壁が続き、色鮮やかな釉薬をかけた陶器のかけらが埋め込まれた歩道を歩行者やウィンドウショッピングを楽しむ人々がのんびりと歩いている。壺屋やちむん通りに向かって緩やかに傾斜した狭くて曲がりくねった路地は、ウチナーヤマトグチ(沖縄大和口)の方言で「すーじぐゎー」と呼ばれる。この路地の途中には、1974年まで活動した陶工が住んでいた新垣家住宅があり、簡素な風景に囲まれた登り窯が土の宮殿のようにそびえ立っている。子宮を思わせる形をした窯の内部は長い間封印されているが、かつてこの窯が支えた陶磁器の伝統は、現在も脈々と受け継がれている。
陶芸の中心地として、壺屋に周辺地域のあらゆる陶芸の技術が集められたのは、意図的な計画によるものだった。1660年、琉球王国の政治·外交·文化の中心であった首里城が焼失し、再建のために大量の屋根瓦が必要となった。そこで、1682年に王国の統治者は島の陶器産業を一か所に集約することを決定し、陶土やその他の材料の調達が容易で、完成品の輸送をより円滑に行える安里川近くの壺屋に、すべての陶工を移住させた。
第二次世界大戦中、那覇市は米軍の爆撃により壊滅的な被害に遭ったが、壺屋は奇跡的に難を免れた。生き残った職人たちは、すぐに工房や薪窯に戻ると、日常生活に必要な陶器の生産を再開。だが、市の人口が急増するに伴い、こうした伝統的な窯から立ち上る煙が問題視されるようになると、薪窯でやちむんを焼くことが困難になっていった。1970年代には、伝統的な技法を守りたい職人たちは本島北部の読谷地区に移住して「やちむんの里」を創設する。一方、壺屋に残った工房は、薪窯をガス窯や電気窯に切り替えて、現在も使用している。



おきなわスローツアーでガイドをしている高野純一さんによると、風水の原理に基づいて綿密に計画されたこの通りと周囲の村が現在の形になり始めたのは1982年のことだという。現在、やちむんの文化と技術の活気ある中心地であるこの村は、沖縄で最も尊崇されるこの工芸品の保護と進化に尽力する多世代の職人家族の共同体によって支えられている。
曲がりくねったメインストリートの中ほどに、そうした窯元のひとつである育陶園の本店がある。育陶園は伝統的な壺屋焼の有名な製造元で、300年の歴史があり、この地域に6つの店舗を構えている。ここの事業の要となるのは、沖縄の認定伝統工芸士である6代目陶主の高江洲忠さんである。店の棚は、唐草模様のモチーフ、魚や海の生き物のイメージなど、彼の独特の線彫り技法で描かれた緻密なデザインの作品で埋め尽くされている。先代陶主で5代目やちむんの名工である高江洲育男さんが独特の作風で制作したシーサーの置物も、棚に静かに鎮座して、購入される日を待っている。
「育陶園の従業員は、それぞれ専門分野を持っています」と話すのは、育陶園の営業部長である高江洲光さん。「私たちの事業は、職人や窯元のスタッフなど製造を担当する部門、販売担当の部門、さらに製品を一般に売り込んで宣伝するための新しい革新的な方法を考える部門の3つに分かれています」
育陶園の代表取締役である高江洲若菜さんによると、職人が一人で制作に没頭する時代は過去のもので、現在では営業やマーケティングが事業に不可欠なのだという。「かつての職人はもっぱら作り手専門で、自らを売り込むことはほとんどありませんでした」と彼女は話す。「いまでは、やちむん作りの難しさや素晴らしさを、お客様に伝えることに専念する人材が必要だと理解しています。これは大きな変化でしたが、必要な変革でした」



育陶園がやちむんの芸術を一般に広めるために行っている重要な取り組みのひとつが、近くの「壺屋焼やちむん道場」における陶芸体験の指導である。このアトリエは、壺屋やちむん道り沿いの豊かな緑に囲まれた赤瓦の木造建築で、建物の中では扇風機が湿った空気をかきまぜながら、その日の体験者を迎え入れる。体験者の腕前は、自分で作る記念品を所望する観光客から、将来職人を目指して本格的に取り組む人まで多岐にわたる。粘土に染まって黄色くなった白いタオルが多くの轆轤(ろくろ)の上の棚からぶら下がっている。簡単なシーサーの置物から、より精巧な作品まで、この場所で生徒たちが制作した作品は、匠の作品と一緒に窯で焼き上げられる。
このやちむん道場の指導者である高安彩百合さんは、作り手の個性は作品に表れると信じている。「最初に作ったシーサーの表情や粘土に彫る線の描き方から、その人らしさが見えることがよくあります」と高安さん。「作風はそれぞれ違い、その人だけのものなのです」
陶器作りは工程こそは少ないが、奥義を極めるには一生かかる奥深い工芸である。土の特性、温度、湿度、時間といった微妙な要素が絡み合うため、やちむん作りは最も熟練した職人にとっても忍耐と根気のいる作業だという。
その工程は、轆轤挽き、つまり轆轤を使って粘土を形成する作業から始まる。作品が望みどおりの形になると、昆虫のトンボに似ていることから「トンボ」と名付けられた手作りの木製の道具を使って寸法を均一にする。この道具に溜まった削りかすは、成形可能な粘土として再利用される。作業後、工房のメンバーが削りかすの山の周りに集まり、小麦粉に卵を混ぜてパスタを作る要領で、リボン状の粘土を水で湿らせ混ぜていく。そして、桶の中のワイン職人が葡萄を踏むように、円陣を組んで粘土を踏みつけ、再び使える材料に作り直す。




やちむんの制作過程でおそらく最も重要な工程は、硬くなった粘土に装飾的な模様を彫る「線彫り」だろう。一か所でも失敗すれば、その作品を商品として販売することはできない。失敗したものは、練習用に使われる。失敗作から得るものは多く、陶芸家がやちむんの技法を習得する上での支えになっているといわれている。
育陶園のやちむん道場周辺の曲がりくねった小道を歩くと、職人が陶器作りの各工程に励んでいるのを窓越しに見られる。小橋川製陶所・仁王窯の窓辺では、会社員生活を経て47歳で修行を始めた遅咲きのやちむん作家で、現在67歳の池野幸雄さんが座っていた。「義理の兄がここの名匠陶工でした」と池野さんは言う。中年になってからやちむんの陶芸家として再出発するきっかけとなった家族への責任感を語ってくれた。「義兄がガンと診断されたとき、私は自分でこの仕事を引き継ごうと決心しました。全力を尽くしますと義兄に誓い、それを守っています」池野さんは話しをしながら、カップや碗を載せた大きなトレイを慎重に高い棚に移したり、巨大なシーサー像の頭部をスタジオの端から端まで運んだりしていた。
小橋川製陶所・仁王窯は、赤江技法の復活と再現で知られている。伝統的な赤色顔料を使用した赤江技法は、かつて失われたとされていたが、小橋川家によって再発見されたと伝えられている。この貴重な素材についての知識こそが、池野さんが休みを返上してでも赤絵の研究を続ける原動力となっている。
「先人たちがこの伝統を守り続けてくれたおかげで、私たちはこの素晴らしい文化を享受できるのです」と池野さんは語る。「彼らが残してくれた贈り物に、毎日感謝するばかりです。そして、私にできる限りのことを次の世代に伝えていきたいと思っています」