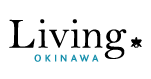沖縄で育った金城由希乃は、それまで自分のことを海好きな人間だと思っていた。だが実のところは、一般の海水浴客となんら違わなかったのだ。海は、バーベキューを楽しんだり、夕日を眺めたり、たまに水に浸かるときの美しい背景でしかなかった。そのような彼女の認識は、18歳のときに初めて受けたダイビングの講習ですべて覆される。
波の下に潜ると、色とりどりの魚や甲殻類、軟体動物が生息する美しい珊瑚の世界が広がっていた。この経験で珊瑚礁の素晴らしさに目覚めた由希乃は、鮮やかで生命力に満ちた珊瑚礁に初めて出会ったときの感動を、多くの人に伝えたいと強く願うようになる。「誰かが珊瑚礁の美しさを褒めると、まるで自分が褒められているかのような気持ちになるんです」と彼女は語る。
そのような由希乃だったが、数年後にシュノーケリングのために近隣の島を訪れた際、使っていた日焼け止めが珊瑚礁に有毒であることを仲間のダイバーから知らされ、大きなショックを受ける。「彼の言葉が頭から離れませんでした」と由希乃は振り返る。「私は海が大好きです。自分は海を愛する人間の一人だと思っていました」


この問題についてできる限り調べた由希乃は、日焼け止めによく使われる紫外線吸収剤のオキシベンゾンやオクチノキサートといった化学物質が、実際には珊瑚の健康に有害であることを知る。それと同時に、欧米諸国には珊瑚に優しい市販の日焼け止め製品が豊富にあるのに対し、日本ではこの問題に対する認識自体が相当に低いことにも気づかされた。最終的に、それまで積み上げた専門知識を活かし、珊瑚礁に安全な独自の日焼け止め処方を開発した由希乃は、2017年から「サンゴに優しい日焼け止め」の製品販売を開始する。その2年後には、地元組織の協力のもと、住民や旅行者が参加できるエコツーリズム活動として、ビーチの清掃活動を行うプロジェクト「マナティ」を始動させた。
沖縄の珊瑚礁のために立ち上がったのは、由希乃だけではない。2018年、沖縄本島の中央部西海岸に位置する恩納村の村長は、村の有名な珊瑚礁を保護するという誓約を立て、恩納村を「サンゴの村」とすることを宣言。沖縄有数のシュノーケリングやダイビングのスポットが点在する恩納村は、国連環境計画と英国に本拠を置く慈善団体「リーフ・ワールド財団」が定めたサステナブル・ツーリズム(持続可能な観光)のガイドラインを、日本の観光地としては初めて採用した。
ハレクラニ沖縄は「SDGs未来都市」に指定された恩納村の地域の取り組みに参加している。「珊瑚礁は海全体の面積のわずか0.2%にすぎませんが、海洋生物の4分の1は珊瑚礁に依存しているのです」と語るのは、ハレクラニ沖縄でサンゴや海の環境保全に取り組んでいる国仲英純だ。「サンゴから栄養を得た海老や小魚が、より大きな魚の餌となり、食物連鎖が続いていきます。今ここで有意義な対策をとらなければ、世界のサンゴは今世紀中に消滅するのではと言われている」と、国仲は懸念する。傍観しているだけでは、珊瑚礁を食物源や収入源、または天然の防波堤として頼りにしている地域社会のみならず、珊瑚礁から産み出される重要な生態系の恩恵を受けている多くの人々が、壊滅的な打撃を受ける恐れがある。

珊瑚礁は海全体の面積のわずか0.2%にすぎませんが、 海洋生物の4分の1は珊瑚礁に依存しているのです。
国 仲 英 純 、ハ レ ク ラ ニ 沖 縄



世界中の珊瑚礁への脅威に対処するには、さまざまな戦略が必要であることに、専門家らも同意している。なかでも、この分野に携わる人々の間で関心が高まっていることの一つが、環境に適合したサンゴの養殖だ。国仲は、サンゴ移植後の生存率を高めるために琉球大学熱帯生物圏研究センターによるサンゴの環境適応能力を向上させる研究をベースにプログラムの再構築を行っている。「たとえ私たちの世代で何も変えられなくても、次世代の人々に(この仕事を)引き継いでもらえます」
次世代のために沖縄の珊瑚礁を護っていこうという話題になると、たいていある人物の名前があがる。由希乃が「沖縄の珊瑚保護活動の第一人者」と呼ぶ金城浩二だ。多種多様な沖縄の珊瑚礁に関する研究は20世紀半ばにまで遡るが、この研究が世界から注目を浴びるようになったのは、1998年の深刻なエルニーニョ現象により、前例のないほど大規模な珊瑚の白化現象が発生し、沖縄の珊瑚の90%(世界中の珊瑚の15%)が失われたときだった。当時、レストランとショップを経営していた浩二は、その悲惨な光景を見て愕然とした。「私はこの海で育ったので、珊瑚がハイビジョンで見るように、とてもカラフルだった頃を知っています。でも、それがまるで白黒テレビに戻ったかのような有様だったのです」


素人の珊瑚養殖家として実験を繰り返し、何年も失敗を重ねた後、浩二はついに野生の珊瑚の繁殖、移植、産卵に成功した。浩二は現在、読谷村の海岸に建設した珊瑚の養殖場「さんご畑」を訪れる人々に珊瑚礁の生態について教育する傍ら、120種におよぶ20万株近くもの珊瑚を育てている。自分の養殖場を「供給センター」と冗談めかして呼ぶが、そこは珊瑚の実験室でもある。そして、近年、温暖な海水域にも耐性のある珊瑚の育種において、革新的な成果を上げている。「珊瑚は地球上で人間よりも長い年月を生き延びてきました」と浩二は語る。「珊瑚には適応力があるのです」
だが、適応力が問われるのは珊瑚だけではない、と浩二は語る。「私たちの世代は、こうなった責任は自分たちではなく他の誰かにあるのだから、私たちが責任をとったり、何か働きかけたりする必要はないと考えがちです」と続ける。「でも、そんな考え方のままで何もせずにいたら、次の世代から『親の世代は自分たちだけいい思いをして、私たちには何も残してくれなかった』と言われてしまうでしょう」