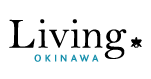誰もが知るワイキキビーチの近くを流れる長さ約3.2キロメートルのアラワイ運河沿いを歩いていたトム・ホーナンさんは、大勢の人が奇妙な球状の物体を濁った水に投げ込んでいるのを目撃した。「おい、そんなことしちゃダメだ!」と彼は集団に向かって叫んだという。それから、その中の1人、チュン·佐藤·史子さんと話をしたところ、彼らは「ゲンキアラワイプロジェクト」というボランティア団体のメンバーであることがわかった。そして、この団体は島でも汚染が深刻な水路の一つであるアラワイ運河を浄化して、2026年までには遊泳や釣りができるようにするという、無謀とはいわないまでも大胆な目標を掲げて活動しているという。この崇高な目的を達成するための彼らの秘密兵器が「ゲンキボール」と呼ばれる地味な泥団子だった。ゲンキボールは、ヨーグルトやキムチそしてパンやビールなどの発酵食品に含まれる善玉菌を混ぜて作られたものだ。
いまでは、トムさんと妻のパムさんは、ゲンキアラワイプロジェクトの熱心な支援者だ。最近開催されたコミュニティイベントでは、トムさんが驚くほど細かなゲンキボールの作成手順を実演している姿が見られた。彼はまず山盛りになった土をふるいにかけてゴミを取り除き、次に米ぬかや酵母そして乳酸菌や光合成細菌がたっぷり入った液体を土に混ぜ、最後にその混合物をテニスボールくらいの大きさの球体にまるめる。筆者も挑戦してみたが、最初は小さすぎ、次は大きすぎという理由で、2個の泥団子が不合格となった。3度目の挑戦の前に「量より質が大事だよ」とトムさんがアドバイスしてくれたおかげで、ようやく「今度はちょうどいいね」と合格となった。
トムさんのようなボランティアは、ゲンキアラワイプロジェクトの原動力だ。同団体のこれまでの活動は、民間の寄付や企業スポンサー、そしてこれまで14万6千個以上のゲンキボール(団体の目標である30万個のほぼ半分)を運河に放流してきた非常に多くの人々の支援に支えられてきたのだ。この日のイベントが実現できたのは、高校2年生のエリー·チャンさんが率いる学生奉仕団体「オハナ·コクア·クラブ」が、ゲンキアラワイプロジェクトのグリーティングカードを販売して千ドルの寄付金を集められたからだ。


「ボランティアの力がなければ、私たちは何もできなかったでしょう。みんなが進んで必要なことをしてくれているおかげです」と、同団体においてコミュニティおよびメディアとの連絡係を務めるチュンさんは語る。歩行器を使って物資を運んでいるトムさんの姿は、まさにボランティアの熱意を表している。そして、カポレイ在住で元ライオンズクラブ会員のローリー・レヴィさんは週に数回、同団体のコミュニティイベントを手伝うため、約39キロメートルの道のりをバスに乗ってやってくるのだとチュンさんは付け加える。レヴィさんは、ジェファーソン小学校にある同団体の保管用コンテナから、運河沿いにある4か所の投入場所へ物資を移動させる作業も、定期的に手伝っている。「ローリーさんなしではイベントを開催できませんでした」と、チュンさんは3歳の娘を抱き抱えながら、完成した泥団子の入ったアルミの鍋を運んでいた。
有用微生物群(略してEM)は、1997年に名護弘道さんによって初めてハワイに持ち込まれた。名護さんは琉球大学の比嘉照夫教授の指導のもと、沖縄で微生物の効用について学んでいた。1980年代初頭、ミカンの堆肥化技術の研究中に農薬中毒を経験した比嘉教授は、微生物に注目し、その有益な性質を偶然発見する。有用微生物溶液を排水溝に流すのはもったいないと思った比嘉教授は、その液体を芝生に撒いた。1週間後、教授は微生物を撒いた芝生が周囲の芝生よりもかなりよく育っていることに気づく。この発見に触発された比嘉教授は、家庭用洗剤から消臭剤そして庭園用肥料まで、さまざまな用途に効果があることが証明された有用微生物群の混合物であるEM•1を開発したのだ。




2006年、ホノルルを襲った大雨により大規模の下水管が破損し、市は1億8,170万リットルもの下水をアラワイ運河に流すことを余儀なくされる。名護さんは、この泥団子が自分の故郷ハワイで力を発揮できるのではと考えた。もともと運河の開発業者は、ワイキキを「太平洋のベニス」にすることを目標としていた。しかし1927年の建設当初から、アラワイ運河は事実上の廃棄物投棄場として利用されてきたのだ。最初は、観光の中心地として急成長するワイキキを支えるインフラ整備のため、かつて湿地帯であったこの地域の排水を行った。さらに、金色に輝くワイキキビーチの海岸に汚れた雨水が流れ込まないように、運河を利用して迂回させる対策がとられた。
しかし、都市部にある水路の水質改善に微生物を利用することの有効性が最新の科学研究で示唆されているにもかかわらず、アラワイ運河でのゲンキボールの使用認可には13年の月日を要する。それは、許可手続きに時間がかかったり、連邦水質浄化法により無許可の物質を水路へ投入することが禁止されていたりしたことによるものだった。ようやくゲンキボールの使用許可が下りたのは、2019年のことだった。
同団体の記念すべき第1回目のゲンキボール投入にさきがけ、ハワイ州保健局の職員が水質基準値を測定するためアラワイ運河に入ると、場所によっては深さ約60センチメートル近くのヘドロに足を取られてしまった。これが、何十年にもわたる汚れた雨水の流入や意図的に行われた廃棄物の投棄による汚染の結果だ。汚泥の広がりだけではなく、腐った卵のような硫黄臭も長い間近隣の住民や企業の悩みの種となっていた。ホノルル市では1970年代初頭には、検査によって高濃度の糞便汚染が確認されたため「運河から採取したものを食べないように」と地元住民に警告する標識を設置していたのだ。


同団体の活動に参加している弘道さんの息子の洸利さんによると、水質検査にかかる費用は依然としてゲンキアラワイプロジェクトの最大の課題の一つだという。ゲンキアラワイプロジェクトは、ハワイ州模範財団のもと非営利団体として認可され、山から海までの流域全体の水源保護を目的とする組織基盤のアプローチを構築する任務を担っているが、連邦政府から約束されていた資金はパンデミック中に枯渇し、市が定期的に行っていた水質レベルの検査も中止となった。それでも、同団体はアラワイ運河を「元気」にするという目標に向け、意欲的に活動している。水質改善が目に見えるようになってくると、彼らの活動にも拍車がかかる。かつてはタールのような黒いヘドロで覆われていた運河の水底が、いまでは砂地や岩場になり、悪臭も消えた。糞便汚染による腸球菌の濃度も低下し、生物の影もなかった運河の一部には、ウェケ(ヒメジの一種)、モイ(ナンヨウアゴナシ)、ハワイアンモンクアザラシなどの在来種も戻ってきた。「ハワイにおけるEM技術が、ここハワイで果たす意義の大きさを実感しています」と洸利さんは話す。いまでは、ゲンキボールはオアフ島のソルトレイクやカリヒ周辺の汚染された水路、日本国外最大の江戸式庭園といわれているハワイ島のリリウオカラニ庭園の広大な鯉の池にも導入されているという。「ここが世界の規範となる場所になる日がきっとくると信じています」
運河に投入された泥団子は、1年かけてゆっくりと運河の底で溶け出し、徐々にその効果を発揮する。「だからこそ、私たちはゲンキボールが大好きなのです。文句も言わないし、彼らには休みも不要です」と言うと、チュンさんは泥団子を手に取り、感謝を込めて頭を下げた。そして「さあ、あなたもがんばってね」と優しく送り出した。