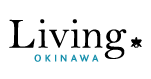頭上で雷鳴が轟く中、平良奈緒さんは沖縄本島北部の大宜味村にある、一家が所有する糸芭蕉(芭蕉布の原料になる在来種の野生の芭蕉)畑の中でも一番大きな畑へと向かっていた。首には「シーグ」と呼ばれる植物の茎を剥ぐための小刀をぶら下げ、激しく飛び回る巨大な蚊から身を守るため、長袖のシャツとズボンという出で立ちをしている。畑にたどり着くと、壁のようにそびえる糸芭蕉の間のぬかるんだ小道を進む。彼女の頭上には、糸芭蕉の葉が緑の天蓋を作り出している。濃い紫色をした糸芭蕉の花に白黒まだらの蝶がとまった。その蝶を見つけた奈緒さんは、「おばあちゃん」と呼びかけて笑う。
いまは亡き祖母、人間国宝の平良敏子さんがなぜこれほどまでに芭蕉布に人生を捧げたのかをもっと知りたいと思い、奈緒さんが故郷の大宜味村に戻る決心をしたのは、いまから10年前のことだった。敏子さんが101歳でこの世を去るまでの数年間、奈緒さんは敏子さんの薫陶を受け、第二次世界大戦後には途絶えかけていた芭蕉布の生産を、かつて栄えた喜如嘉地区で見事に復興させた祖母の情熱と粘り強さを目の当たりにした。
この地域は頻繁に台風の影響を受ける。敏子さんは100歳を過ぎて自転車に乗れなくなったときでさえ、台風が過ぎ去るたびに必ず糸芭蕉の畑を見に行っていた。「畑の様子を見に行ける人は他にもいたのですが、祖母は自分の目で確かめたかったのです」と話す奈緒さん。敏子さんを乗せて車で畑の見回りに行くと、非常に喜んでくれたという。敏子さんが工房での作業時間を減らしたのは人生最後の半年になってからのことだったが、それでも一日の作業の準備をするために、毎日夜明け前に工房に姿を見せた。「人間国宝の使命は、90歳になったからといって終わるようなものではありません」と、奈緒さんの母である平良美恵子さんは語る。美恵子さんは、2022年に亡くなった敏子さんが残した芭蕉布の制作全般を管理している。「100歳を過ぎても自己研鑽を重ね、次世代を育てる使命があるのです」


福井県出身の美恵子さんは、芭蕉布職人の家庭に入る以前から、義母の仕事をよく知っていた。琉球民芸に興味があった美恵子さんは、1972年に沖縄が日本に返還された後、沖縄へやって来る。一方の敏子さんは、戦後まもなく倉敷市で民藝運動のリーダーとなった染織家の外村吉之助さんに師事する。1年間正式に染織を学んだ後、本格的に芭蕉布織りに取り組み、美恵子さんが沖縄に来た頃には、この工芸に多大な貢献を果たした人物として知られていた。
美恵子さんによると、かつて外村さんは「敏子さん、心ここにあらずだね。うわの空だと、機織りの『シャン、シャン、シャン、シャン』というリズムが崩れてしまいますよ」と言ったことがあるという。「それは技術的な指導というより、内なる静寂の学びだったそうです」
沖縄県平和祈念資料館で流れる証言ビデオの中でも、敏子さんは恩師について次のように回想している。「外村先生は日頃から『織物は心から生まれる、織物には心が表れる』とおっしゃっていました。先生は技術だけでなく、織物に必要な心構えも教えてくださいました」
倉敷から沖縄に戻った敏子さんは、戦争で村の多くの家が破壊されたことを目にする。マラリアを媒介する蚊を駆除するため、糸芭蕉の農園もアメリカ軍に焼き払われていた。織物に対する新たな感性と、沖縄に戻っても地元の織物を存続させてほしいという倉敷の人々の願いに突き動かされ、敏子さんは身の回りにあるもので作品を織り上げることにした。再び糸芭蕉を栽培しながら、敏子さんと家族は家で蚕を育てて糸を取り、廃棄処分された軍用毛布やテントを解きほぐして綿を取り出し、織物に再利用したのである。


「昔は、芭蕉布は家族総出の仕事だったのです」と美恵子さんは語る。「おじいさんが畑の世話をし、おばあさんが糸を作り、子どもたちはどんな手伝いもしていました」。ところが、戦後になると村の芭蕉布産業が衰退して経済的な見通しが厳しくなり、男性たちの多くが大工仕事を求めて、大宜味村を離れ、都市部へ出ていった。
そこで敏子さんは村の女性たちに芭蕉布の生産再開を呼びかけ、喜如嘉の織物技術を守るために協同組合を結成する。そして皆で協力して、喜如嘉独特の複雑な絣(かすり)模様やテーブルリネン、クッションなどの新しい製品も開発した。この取り組みは駐留米軍家族の間で人気を博し、喜如嘉の芭蕉布文化の美しさと価値が再び認められるようになった。
芭蕉布織物工房の機織り室には、昔と同じように、いまも湿った熱気が立ち込めている。次の作業に備えて加湿器を使い、デリケートな芭蕉の繊維をしなやかで切れにくい状態に整えているのだ。木々で鳴くセミの合唱に、穏やかな糸車の音と扇風機の低い唸りが加わる。隣の部屋では、別の音が静寂を破って響いている。美恵子さんが、逆さにした湯呑み茶碗を布地に沿わせ、木の床の上で長くしっかりとしたストロークで何度も擦りながら布目を整え、布に滑らかな質感と光沢を与えている音だ。
敏子さんが工房見学ツアーを始めたのは、糸芭蕉が「喜如嘉の芭蕉布」として知られる名高い織物へと仕上げる緻密な作業を一般の人々に知ってもらいたいと考えたからだ。それは、巧みな技術や数字的正確さ、そして何か月にもわたる手作業を要する。恐ろしく気の長く複雑な工程だ。「晩年の彼女の関心は、芭蕉布が世界の中でしっかりと居場所を確立することに向いていました」と美恵子さんは語る。敏子さんは、とくに博物館や美術館の学芸員に働きかけ、彼らのコレクションを通じて芭蕉布が世界に共有され、永く保存されることを願っていた。



「目的は芸術作品を作ることではありませんでした」と美恵子さんは即座に明言する。「人々が触りたくなる、着たくなる、そんな生地を作ることだったのです」。敏子さんはプロデューサーとしての視点を持ち、労働条件の改善、生産基準の向上、さらに多くの人々がこの工芸技術を学び洗練させる機会を促進しながら、素材の本質を引き出し、低品質の繊維でさえもその魅力を引き出す技に長けていた。「布そのものを変えるというより、布を取り巻く環境を変えるという点で、彼女の功績は大きかったと思います」と美恵子さんは語る。
特徴的な模様、豊かな伝統、そして苦労の末に勝ち得た名声により、芭蕉布を織ることに興味を持つ若者は後を絶たないと奈緒さんは話す。だが、真剣にこの技術の習得に励む者はほとんどいない。「良い糸を作るには、良い糸芭蕉が欠かせません」と話す奈緒さん。機織りの仕事は、糸芭蕉が収穫される3年前から畑で始まると説明する。「芭蕉布を学びに来ても、ここでの生活に馴染めない人もいます。『草むしりに来たんじゃない。畑仕事をするために、ここに来たわけではない』と言って立ち去る人もいます」
この厳しい現実こそが、奈緒さんが喜如嘉に留まり、高齢の職人とともに働き続けている理由である。職人の中には、幼少期から彼女の人生に深く関わってきた人もいる。「80歳、90歳、100歳になっても、糸を作り続けたいと言うなら、私はここに残って彼女たちのために繊維を収穫してあげたいのです」と語る奈緒さんの目に涙が溢れる。「誰かに命令されたわけでも、義務感でやっているわけでもありません。ただ、頼まれるたびに、私がやらなければと思うのです」
奈緒さんは、毎朝学校に向かう途中、喜如嘉の女性たちが縁側に座り、軒下で芭蕉布の糸を結んでいる姿を目にしたことを覚えている。その姿はまるで風景の一部のようだったという。喜如嘉の芭蕉布の伝統を存続するということは、この工芸を村の命ともいえるその精神を守ること、そして家族のようにお互いを思いやるコミュニティの価値観を受け継ぐことにほかならない。「携わる者の心が一つにならなければなりません」と美恵子さんは語る。 「心を一つにするから、芭蕉布には作者の銘がありません。なぜなら、芭蕉布はみんなの努力の賜だから」