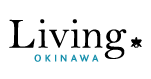ウチナーグチ(沖縄の伝統的方言)には、「行き逢りば兄弟(イチャリバチョーデー)」という言葉がある。「ひとたび出会えば皆兄弟や姉妹になる」という意味だ。祖国に帰れば、家族として迎えてもらえる。 私を含め、ディアスポラ(「故郷を離れた人々」)にとっては、なんとも頼もしく安心感を与えてくれる言葉だ。しかし、ある雨のふる冬の夜、ハワイのオアフ島にあるカリヒバレーで、2人のウチナーンチュ、エリック・ワダとノーマン・カネシロに出会ったとき、私はこの言葉の本当の意味を理解していなかったことを悟った。ハワイ生まれの彼らは、ハワイに沖縄の芸術文化を永続させるために活動する舞台芸術集団「御冠船歌舞団(ウクゥワンシンカブダン)」の共同創設者だ。
「それって力強い言葉だよね? でも、ただ奪い取っていくだけの植民地的視点からこの言葉を考えると、何のお返しをすることもなく、皆の友情や愛を得る権利があると主張していることになるんだよ」と、カネシロは言う。
1900年1月、26人の沖縄人(「オキナワン」)の契約労働者が、プランテーションで働くためにハワイに到着した。それがきっかけとなり、何千人ものオキナワンが故郷を離れ、波のように続々と海外へ移住することになった。その後、祖国沖縄の人々は2つの帝国間の残酷な戦いに巻き込まれ、日本による植民地化とアメリカの軍事占領による爪痕は今日まで残っている。一方、故郷を離れたオキナワンたちは、異国の地に居場所を築きつつも、差別や同化への圧力に直面しながら暮らしてきた。現在、ハワイには約10万人のオキナワンがいる。
このような状況の中、たとえ親戚だったり、祖先が同じ村の出身だったりしても、5世代も前の移民、祖国を隔てる広い海、言葉の壁、戦争や植民地化といった大きく異なる経験などにより隔てられてきた人々が、「チョーデー」として出会うことに、どのような意味があるのだろうか?


御冠船歌舞団はハワイのオキナワン・コミュニティに、先祖の島と 自分たちを育ててくれた島の相互責任の意識を植え付けることを 目的としている。
ワダとカネシロは2007年、音楽と舞踊を通じてハワイと沖縄のつながりを育むべく、御冠船歌舞団を創設する。実は、その創設には、さらに深い目的があった。それは、ハワイのオキナワン・コミュニティに、祖先の島と自分たちを育ててくれた島には相互的に責任がある、という理念を植え付けることだった。
「そこにあるのは、強いクレアナ(ハワイ語で「責任」の意)なんだ」。自宅に設えたダンススタジオの床に座り、ワダは語る。身に着けた青いTシャツには、「ola i ka wai(水は命)」というハワイ語の格言が刻まれていた。頭上には、沖縄古典芸能の玉城流の師範たちの肖像画が、尊敬するウヤファーフジ(「ご先祖様」)のように掲げられている。「ウチナーグチではそれをフィチ ウキーンというんだ」。この言葉は、「引っ張る」「受け継ぐ」という意味の「フィチュン」と、「受け入れる」「大切にする」という意味の「ウキーン」という2つの語根を合わせたもので、祖先から受け継いだ義務に対する責任感を表している。
沖縄の祖先とのつながりやウチナーンチュとしてのアイデンティティを強く求めていたワダとカネシロは、共に少年時代から舞踊と三線を学んでいた。カネシロがワダと出会ったのは16歳のときだった。ワダはカネシロより10歳年長だったが、芸術への熱い情熱を抱く二人はすぐに意気投合する。彼らにとって芸術とは、練習するだけのものではなく、自らを理解するための羅針盤のようなものだったのだ。
二人は沖縄で学び、生きる術としての文化活動に専心しながら、沖縄古典芸能界の階段を昇っていった。ワダは沖縄舞踊の師範となり、カネシロは音楽の世界で同じく頂点を極めた。共に日本語とウチナーグチを学び、文化や礼儀にも通じている。
「たった5分の歌の裏には、それぞれの歴史や世界があるんだ」と、カネシロは感嘆して言う。自ら飛び込んだ世界を探求するうちに、彼らは文化活動を政治的なものとしても捉えるようになった。「自分自身の言語で話すことだって、一種の(政治的な)活動なんだよ」と、ワダは言う。

1879年に日本に併合される前、沖縄は琉球王国と呼ばれる独立国家だった。ハワイ同様、併合は言語や文化を組織的に抑圧し、それにより今日、沖縄の伝統的な言語は絶滅の危機に瀕している。多くの文化的な慣習も失われてしまった。ワダとカネシロが彼らのグループに名付けた「御冠船歌舞団」という名前は、この王国の歴史に由来するもので、「冠船」は中国から琉球に向けて、国王の戴冠式に参加するための大規模な使節団を乗せて航海した船にちなんでいる。冠船が到着すると、中国使節団をもてなすために、ウクヮンシンウドゥイ(御冠船踊り)と呼ばれる趣向を凝らした音楽と舞踊が披露され、これが沖縄の古典芸能の基礎となったのだという。
御冠船歌舞団は、ハウナニ ケイ・トラスクやリリカラー・カメエレイヒヴァといった、ハワイの民族独立活動家から大きな影響を受けた。そして、琉球人の主権回復と植民地支配や占領が消し去ろうと試みた民族の文化と歴史を取り戻す術として、舞踊や音楽に着目したのだ。
それは、ハワイにおいてはオキナワン・コミュニティのために演奏することだけでなく、沖縄の豊かな歴史をハワイの人々に広め、ハワイの土地に入植したオキナワンとしての役割と向き合うことを意味していた。「僕たちは植民地化、同化、入植者、差別などという言葉を使って話をしたんだけど、最初はみんな、とくに年配の人々は受け入れようとしなかったんだ。そのあたりは、彼らにとって、すごく話したくない部分だったからね」とワダは言う。しかし、沖縄とハワイの聖地が冒涜されていること、中でもそれが沖縄に現在32の基地を置いている米軍によるものであることと関連づけることで、会話は徐々に変わっていった。
ハワイ生まれのウチナーンチュでありながら師範の資格を持つワダとカネシロは、沖縄ではアウトサイド・インサイダー(外からの仲間)としてのアイデンティティが、故郷の人々と特異な親近感を生むことに気付いた。音楽家だからこそ、親密な雰囲気の中で沖縄の歴史についての奥の深い話ができた。また、海外からの訪問者だからこそ、このような議論によって生じた家族間や世代間のトラウマから少し距離をおける。やがて彼らは、自らが長い間隠されていた傷の手当てをしていることに気付いた。「僕たちは新たなレベルに到達したんだね。長老たちは、自分の子どもたちに伝えるのが難しいことでも、僕たちには話してくれた。いずれ次の世代には伝えないといけないことだから。」この深い信頼関係は、彼らにとってハワイと沖縄の相互理解の重要性を示すものだった。かつて沖縄に「本物であること」と「力強さ」を求めたワダとカネシロは、祖国のオキナワンたちとともに先住民族としてのアイデンティティを取り戻し、共に歩んでいくという機会を得たのだ。

ワダとカネシロそして御冠船歌舞団のメンバーたちは、何年もかけてその活動を大幅に拡大してきた。共同ディレクターのキース・ナカガネクによる歌三線教室、理事のブランドン・イングによるウチナーグチ教室、沖縄の文化や政治に関する月1回のワークショップ、そして毎年世界中からオキナワンをハワイに招き、自分たちがどのような民族であるかについて意見交換を促す「ルーチュー・アイデンティティ・サミット」などを開催してきた。
そして、ハワイおよびカナカマオリ(先住ハワイアン)に対して抱くクレアナに、オキナワンはさらに焦点を当てるようになる。2019年、ハワイ島マウナケアの天体望遠鏡建設反対運動が巻き起こった際には、御冠船歌舞団はオキナワンの代表者を率いて、この先住ハワイアンの聖なる山を守る人々と連帯し、ホオクプ(ハワイ語で「贈り物」の意)を捧げた。2021年に発生したオアフ島のレッドヒルにおけるジェット燃料流出事故後には、米軍によるハワイと沖縄の帯水層汚染の重要な関連性を示すパネルディスカッションを開催した。最近では、オキナワンの先祖の遺骨を本来の安住の地に送り還す取り組みにも携わっている。
御冠船歌舞団が長年にわたり成長してきた過程を思い出しながら、ワダはこう言った。「フィチ ウキーンに立ち返るんだ。この言葉は、すごくたくさんのものとつながっているから。自分たちが誰であるか、自分たちはどうあるべきかということに」つまり、それは海を渡ったディアスポラとして生きることの重荷であり、特権なのだ。2つの異なる故郷に対する責任を受け継ぐのだから。
「家族である以上、ただ家に立ち寄って、食べたり飲んだりするだけではすまない。後片付けをし、家を大事にする。大変なときにも、戻ってきて顔を出す。それが チョーデーであるということなんだよ」と、カネシロは付け加えた。