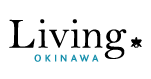本部町にある山城とうふ店の工場の窓辺が、朝の光でほんのり明るくなり始める。だが、74歳の会長、山城好充さんは、すでに何時間も前から作業に取り組んでいた。湯気が立ちのぼる豆乳の大釜の前に立ち、長年の経験で鍛えられた眼差しで、表面に浮かぶ泡をじっと見つめている。約40年にわたって豆腐作りに携わり、培った直感を頼りに、山城さんは微妙な兆しを見逃さず、豆乳から沖縄名産のゆし豆腐を作るための凝固剤と調味料を加える瞬間を見極める。
そして、その瞬間がくると山城さんはにがり(凝固剤)と塩が入ったバケツに少量の豆乳を移す。その混ぜ合わせたものを大釜に戻すと、ほどなくして豆乳は固まり始め、まるでやわらかい雲のように浮かび上がり、おぼろ状に変化していく。ひしゃく代わりの片手鍋で、丁寧にすくい上げた乳白色の擬固物をバケツに移して、水を張った盥(たらい)の中で冷やす。

「ゆし豆腐は一旦火を止めて、余熱で調理することによって、最高の食感とやわらかさが生まれるのです。ちょうど焼いたあとのステーキに、余熱でじんわりと火が通っていくように」と、山城さんの娘で店の代表取締役を務める仲里奈理美さんが説明する。家族が守り続けてきた少量仕込みの豆腐作りを学んで数年になる奈理美さんだが、にがりと塩を加える重要な作業は今も父親が担当しているという。この作業はタイミングがすべてだ。ほんの少し遅れると、大釜の中にできる擬固物が焦げてしまい、本来の豆腐のやさしく香ばしい風味が、強い焦げた香りへと変わってしまう。「これは企業秘密なんだよ」と山城さんは静かに笑う。そして、この慎重を要する作業もいずれは奈理美さんに教えて託すつもりだと話した。
「私の母がこの工場を始めた頃は、にがりや塩の代わりに、すぐそばの入り江の海水を使っていたんだ」と山城さんは懐かしそうに語る。今ではその海水は汚染され、豆腐作りに使えなくなってしまったという。山城さんの母親のトミさんが豆腐作りを始めたのは、第二次世界大戦後まもなくの頃だった。アメリカ政府が、沖縄の人々に大豆などの物資を配給し、経済復興や地元産業の建て直しを図っていた時代である。当時、崎本部地域には豆腐店が少なくとも3軒あったが、今でも残っているのは山城とうふ店のみだ。



本州の豆腐とは異なり、ゆし豆腐はゆるく、とろんとしたプリンのような口当たりで、調理後すぐ食べる。たいていはその日のうちに食べきるものだ。山城とうふ店では、ふわふわのゆし豆腐を湯気が立つほど熱々の状態で販売しているほか、ゆし豆腐に重しをして作るずっしりと重みある「島豆腐」も作っている。工場では厚揚げや豆腐作りに必要な原材料も手がけており、今なお沖縄伝統の手作り豆腐を守り続けている数少ない店の一つである。
ほかの豆腐と同じように、ゆし豆腐作りも水に浸した大豆をすりつぶし、豆乳とおから(豆腐粕)に分けることから始まる。おからは昔から家畜の飼料として再利用したり、家庭料理に使われたりしてきたが、今はそのほとんどが廃棄されてしまうのだと奈理美さんは話す。
「豆腐作りを身近に見て育ちましたが、その過程でたくさんのおからが捨てられているのに気づいたんです」と、山城さんの長女である具志堅あきのさんは語る。小さい頃から、実家の工場で作った豆腐を使って新しいアイデア料理を試すのが好きだったというあきのさん。大人になり、その興味はさらに深まったという。やがて、おからを使ってマフィンの生地が作れることを知った。



「趣味から始まったんですよ」と語るあきのさんは、豆腐を使った料理や甘菓子専門のカフェ&スイーツ店SOYSOYを立ち上げたきっかけについて語る。「豆腐のおいしい食べ方をあれこれ試すのが本当に楽しくて、いろいろなお菓子や料理を作っていたのです。そうこうするうちに、豆腐にはこんなにたくさんの使い道や楽しみ方があるんだってことを、もっと多くの人に知ってもらいたいと思うようになりました」
SOYSOYを立ち上げてから10年、あきのさんは島内に3店舗を展開するまでに事業を拡大した。「とうふ屋の娘として、いつかは海外にも広げていけたらと思っています」とあきのさんは語る。「とびきりおいしい沖縄のソウルフードであるゆし豆腐を、世界中の人々に届けたい。それが今の私の夢なんです」


日本の食品衛生規制のために、店頭での販売は難しい。今日、伝統的なゆし豆腐を作り続けているのは、ごく少数の小規模生産者のみだ。多くは小売店舗を持たず、直接顧客に販売する方法をとっている。そういった状況にもかかわらず、奈理美さんは、愛され続けてきた郷土の味に再び関心が集まりつつあると感じている。ゆし豆腐の復活は、できたてを熱いうちにその場で味わうという沖縄の食文化である「アチコーコー」の心が今も息づいている証なのだ。
そろそろ昼が近づく頃、工場の入り口に二人の女性の姿があった。山城とうふ店の評判を口コミで耳にし、家族代々で受け継がれてきたゆし豆腐を買おうとやってきたという。あと1時間ほどかかると奈理美さんが告げると、女性たちはにこやかにうなずいて、豆腐が冷めるまでゆっくりと待っていた。